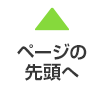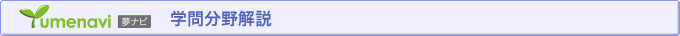学問分野解説

27.数学
奥深い数学の世界を究める
数や図形の性質・関係を研究して、公式・証明などの法則化を図る論理的思考の学問である。純粋数学と応用数学に大別される。純粋数学は抽象的な概念を論理的に考える理論体系を主とし、数の性 質や関係、定理や方程式の解法などを研究する「代数学」、図形や空間の性質を研究する「幾何学」、微分・積分をベースに物理学とも関わる「解析学」などがある。
数学の知識を社会の中で生かす
応用数学は、コンピュータを積極的に活用してさまざまな問題を数値化するなど、自然科学、社会科学や工業分野と関連している。プログラム理論や確率論、社会科学系の分野でも応用されるゲーム理論なども応用数学の領域である。プログラミング理論や計算法のアルゴリズム、情報通信に欠かせない暗号理論、社会科学の諸問題の効率を最大限に高めるオペレーションズ・リサーチなども研究対象となる。
| 将 来 |
主な就職先としてはシステムエンジニアやプログラマーをはじめ、製造業や情報通信関連のサービス業などが挙げられる。教員免許を取得して、数学の教員になる人も多い。また大学院への進学率も比較的高い。 |

28.物理学
素粒子から宇宙まで自然界の法則を解明する
自然界の物理現象の観測と実験的検証を通して、その法則を証明し、理論的解釈を与えることを目的とする学問である。対象は非常に幅広く、ミクロの世界の素粒子・原子・分子から地球・宇宙まで、自然界のすべての事象を対象としている。科学技術全般への応用範囲が広い学問である。
実験やシミュレーションで理論の構築をめざす
「原子・素粒子物理学」では物質を構成する原子や物質の究極の構成単位である素粒子を探究する。「物性物理学」は電子や原子の運動から物質の性質を解き明かし、半導体や超伝導の研究につながっている。「宇宙・天体物理学」では宇宙の誕生の謎やブラックホールなどを研究する。研究手法としては、現象の実験的検証を行う場合と、数式やコンピュータシミュレーションをもとに理論構築をめざすものがある。
| 将 来 |
大学院への進学率が半数に近く、修士課程の後に企業の研究部門への就職を見据える例が一般的。大学や国の研究機関に就職する人もいる。一般企業では、電子機器、機械、ソフトウェア、システムや情報分野が中心。 |

29.化学
生活に役立つさまざまな物質を作り出す
固体、液体、気体など、あらゆる物質とその性質や化学変化の仕組みを調べて分析し、暮らしに役立つ新しい物質を作り出す学問である。薬品や新素材、半導体、セラミックなどの開発につながる物質研究をはじめ、バイオや光通信といった多彩な分野に接点をもつ。物質と環境の関わりを分析して、環境保全技術を開発する研究も行われている。ナノテクノロジーや高分子ポリマー、有機ELなど新しい機能や性質をもった素材や物質で生活は大きく進歩している。
物質の合成、反応、変化のメカニズムを解明する
その研究分野は、炭素を含む物質の合成・反応・変化を研究する「有機化学」、金属やガラスを扱う「無機化学」、物質の構成や状態変化のメカニズムを探る「物理化学」、物質の計量や解析を行う「分析化学」、タンパク質などの生体に関する化学反応を対象とする「生化学」などに分かれている。
| 将 来 |
一般化学産業のほか、金属・医薬品・食品業界や専門書を扱う出版業界など選択肢は幅広い。企業での研究者のような専門家をめざすなら、大学院を修了して、より高度な知識を身につけることが望ましい。 |

30.生物学
生命と生物の仕組みの不思議を解き明かす
人間・動物・植物・微生物などの生命体を対象に、自然界での活動や、個々の生体現象を解明する学問である。遺伝子レベル、細胞レベル、内部器官の機能や構造、生物の行動や生態など、顕微鏡の中のミクロの世界から野生の動植物の生息地域の現地調査までもが研究対象となる。生態と環境の関係など、生物を取り巻く環境との関わりもテーマとなる。
生物に迫るためのさまざまなアプローチ
生物を対象に、系統的に分類する「分類学」、進化を研究する「進化学」、生態を解き明かす「生態学」、行動を分析・研究する「行動学」。生体を対象に、その仕組みを解明する「生化学・生理学」、生命の誕生や器官形成を探る「発生学」、遺伝子の役割を解明する「遺伝子学」、細胞を対象とする「細胞生物学」や「分子生物学」などの分野がある。クローンやゲノム、再生医療などの研究分野とも関連が深い。
| 将 来 |
企業に就職する場合にも高い専門性が求められるので大学院に進む人が大半。医薬品・食品・化粧品・醸造などの分野で商品開発という進路が開けている。研究者として大学に残るほか、公的な研究機関に入る人もいる。 |

31.地球科学
地球と自然について学ぶ
46億年前に誕生した地球の謎を解き明かし、さらに温暖化やオゾンホール、エネルギー問題など、地球の未来を左右する自然現象の問題解決をめざす学問が、地球科学である。地層や化石、気象、生物を手がかりに、地球という存在そのものに焦点を当てる。また、地震・津波・火山噴火・竜巻などの自然災害の現象の解明や防災にも寄与することをめざす。
地球の不思議に壮大なスケールで挑む
研究のスケールは大きく、地球の誕生から現在までのすべての事象が対象となる。基礎科学の分野としては、地質学、岩石学、鉱物学、気象学、地震学、地球物理学、自然地理学などがある。また応用分野としては、地球環境科学、天然資源開発、防災地学、さらに、太陽や月、宇宙空間を対象とする地球惑星科学などがある。研究では実験のほか、現地での野外調査や観測によるデータ収集なども重視される。
| 将 来 |
多くの人が大学院へ進学した後に、環境計画・都市計画関連、エネルギー関連、土木・建設関連企業などで専門職になる。IT産業や製薬会社への就職も目立つ。公務員になり、建設・土木・気象などの省庁で働く人もいる。 |

32.機械工学
ものづくりの基礎を支える技術や理論を学ぶ
「ものづくり」の基盤を支えている重要な学問領域で、ものをつくるための技術やその原理・方法論を系統立てて研究し、機械や生産のためのシステムを構築するためのテクノロジーを学ぶ学問である。分野としては材料の強度や特性、新素材の開発などを行う「材料系」、エンジンや発電プラントを研究する「熱・流体系」、部品の設計や製作・加工について学ぶ「設計・製作系」、機械の制御技術などを開発する「計測・制御系」の4つに大きく分かれている。
研究対象のスケールも種類も多種多彩
研究対象は自動車やロボット、工作機械、精密医療機器、人工臓器、マイクロマシンなど、そのスケール・種類ともに多彩なことと、異分野の研究と連携が進んでいることが特徴。研究成果はものづくりだけでなく、医療福祉、環境問題、エネルギー分野などで幅広く活用されている。
| 将 来 |
自動車や造船、家電といった機械関連、重工業などが挙げられるが、機械工学の知識は各方面の生産技術で生かせるので、食品・繊維など多様な製造業でも活躍できる。研究職での就職希望なら大学院進学を検討したい。 |

33.航空・宇宙工学
空と宇宙を舞台に描く壮大な夢とロマン
航空機やロケットの開発、宇宙ステーション計画、人工衛星の利用などに必要な先端科学技術を生み出す、スケールの大きな学問である。小惑星探査機「はやぶさ」の帰還や、日本人宇宙飛行士の宇宙ステーションでの活躍などに見られるように、宇宙の謎を解明し、人類の宇宙への進出を実現することをめざす。
「速くて、安全で、環境にやさしい」をめざす
空気の流れや抵抗などの問題を研究する「流体力学」、機体の設計やその材料などについて研究する「構造力学」、航空機やロケットのエンジンなどの開発を行う「推進工学」、機体の姿勢や軌道制御などのシステムについて研究する「制御工学」の4分野がある。航空機は安全性はもちろんだが、環境に配慮した燃料効率などが課題となっている。未知の領域も多く、常に新たな課題に取り組める学問分野である。
| 将 来 |
航空機メーカーや航空会社のほか、電機メーカーの宇宙・ロボット部門、精密機器メーカー、鉄道関連企業などへの就職や、航空機整備やパイロットの資格取得を見据えた就職が多い。航空宇宙関連の研究所、関連官公庁などにも進出している。 |

34.電気・電子工学
電気をめぐる新しい技術を開発する「電気工学」
エネルギーと情報伝達媒体という、電気の2つの側面を研究の軸とするのが電気・電子工学の学問分野である。電気工学は電子の流れをエネルギーとしてとらえ、主に発電、電力輸送、電動機の制御などについて学ぶ。効率のよい発電や蓄電、輸送を研究するとともに、超伝導やプラズマ、太陽光発電や風力発電なども研究対象となる。
コンピュータや通信技術を支える「電子工学」
電子工学は情報伝達の媒体としての電子を考えるもので、コンピュータや半導体、LSI(大規模集積回路)、電子機器など製作の基礎となる学問。ソフト・ハードやネットワーク技術の開発といった、電子の性質の応用に関わる研究開発を行う。回路やシステムの設計から、情報通信、デバイスや材料の開発など研究領域は幅広い。電気・電子工学の技術を医療分野などほかの分野と融合しようという動きも出てきている。
| 将 来 |
家電製品やコンピュータのハードウェアなどのエレクトロニクス、情報関連産業、エネルギー関係はもとより、通信、ソフトウェア、材料関連の産業、金融機関などで技術開発に携わる人が多い。大学院への進学率も高い。 |

35.通信・情報工学
情報化社会の要、通信技術の進歩をめざす
コンピュータ、情報、通信に関するあらゆる技術を研究する学問である。インターネットの登場、携帯電話の普及とその通信システムの進歩によって、情報のネットワークが一気に拡大し、情報のブロードバンド化、モバイル化、高速化は生活の利便性を高めている。こうした技術開発を担っているのが通信・情報工学だ。主要な研究分野は3つに分かれる。
情報とは何か、情報をどう生かすかを学ぶ
1つ目はコンピュータのハード・ソフトと通信・情報処理を総合的な観点から学び、情報伝達技術の向上や環境について考える分野。2つ目は情報とは何かという問題から情報の扱い方を考え、それを確率・統計、情報理論、ソフトウェアの研究に生かす分野。3つ目は情報の産業部門への応用を図る分野で、管理工学・経営工学などと関連が深い。産業分野で情報を利用するためのシステムや機器の開発なども行う。
| 将 来 |
システムエンジニアのような直接情報に関わる職業、オーディオや家電などの電気・電子機器メーカー、金融や流通、製造、サービスといった各方面の企業が主な就職先となる。即戦力をめざし修士課程へ進学する人もいる。 |

36.建築学
どの時代にも、どの地域にも「建築」はあった
建築学は、芸術と融合した科学として、機能性・快適性・強度・安全性、環境に合ったデザイン性などをそなえた建物を造る知識と技術を研究対象とする。建物の設計やデザイン面に注目が集まりがちだが、最近では防災という観点から耐震性など、その構造の強度や安全性も特に重要な要素となっている。
デザインだけではない、建築学の学び
「計画系」は建築設計を軸に、建築史や建築計画、都市開発など、建築物や街のあり方などを研究する。「構造系」は防災の観点から、建物の耐震構造や建築材料の性質、強度などの具体的な技術や材料について学ぶ。「環境系」は、建築物と光、音、空気、自然環境などとの関係を研究していく。建築物の設計にはこれらのそれぞれの分野の総合力に加えて、空間表現力、デザイン力などが求められる。
| 将 来 |
ゼネコンや設計事務所で設計、構造計算、現場での施工・管理に携わったり、官公庁に入り都市計画に関わるなどの職種がある。実務に関わりながら建築士をめざす人も多い。広告や金融、不動産関連に就職する人もいる。 |

37.土木・環境工学
生活基盤・ライフラインを造り・支える「土木工学」
土木工学は、社会と暮らしを支えるための学問である。道路・鉄道・橋といった交通施設、発電所などのエネルギー施設、河川海岸の堤防、上下水道、ダムや、水道・ガスなどのライフラインを構築する技術を研究する。建設のための技術だけではなく、その前提となる計画・調査・設計の知識や、建設後の管理・運営の技術や知識も習得する。土の力学的性質を学ぶ土質力学、水の流れに関する力学について学ぶ水理学、地盤力学などの基礎的な知識も必要とされる。
自然環境と人間の暮らしの調和を考える「環境工学」
環境工学は、自然環境と人間生活との調和を図りながら社会システムを形成することをめざす学問。居住環境の問題から都市環境、さらに地球環境の問題までを対象とする。工学的な知識はもちろんのこと、社会学的な知識など幅広い視点からのアプローチが求められる。環境との調和は人類の大きな課題である。
| 将 来 |
大半はゼネコンで公共工事などに従事する。鉄道・不動産・コンサルタントといった業種でも知識と技術を生かせる。環境工学の場合は、土木工学と同じ分野のほか、上下水道整備を請け負うコンサルタント会社などに勤める人も多い。 |

38.材料工学
材料の研究開発はものづくりの原点
さまざまな材料について、化学の知識をベースに、その構造・機能などを工学的に研究し、新機能を発見したり、新しい材料を開発したりする学問。対象は半導体材料やセラミックス、燃料電池や超電導の材料、磁性材料、いろいろな機能を持つ合金、医療分野で使われる人工の骨や血管などの生体材料までと幅広く、ほかの分野の発展にも重要な役割を果たしている。
可能性を秘めた新材料で社会を変えていく
その研究領域は、材料の開発にとどまらず、製造プロセスから加工技術の開発、実用化のための研究までを行う。航空機にも使われる軽量で強度の高い炭素繊維や、伝導性に優れ強度も高いカーボンナノチューブなど新材料は、既存の材料と置き換えることによって新たな可能性を生み出している。環境との調和の観点からも、高機能、省エネルギーで、環境に負荷の少ない材料の開発が求められている。
| 将 来 |
製鉄・非鉄金属会社、商社の鉄鋼貿易部門などで、従来から即戦力として期待される。最近は多種多様な産業分野で技術の複合化が著しいことから、電気・機械・自動車・繊維・石油・化学といった業種の企業に就職する人も少なくない。 |

39.応用物理学
物理学の知識を実用に生かす
応用物理学は、これまでに得られた物理学の原理や理論、解明された物質の構造や性質、現象や法則を活用して、実際に社会で役立つ技術を研究・開発する学問。物理学は理論や法則を解明するために実験や考察を行う側面が強いが、応用物理学はより実用的な側面をもち、製品や技術を開発することをめざすので、産業や経済分野とも関連が深い。
未来を切り開くための技術を開発する
代表的な研究分野には、超電導や半導体などを対象とする「物性物理」、電子素子物理・電気回路について研究する「計測・エレクトロニクス」、情報理論や数理モデルに基づく「情報・制御」などがある。応用物理学はトランジスタや半導体レーザー、高性能磁石などを生み出し、技術の未来を切り開いてきた。大学での学びは、材料、機械、情報といった領域の、工学的な科目が中心になる。
| 将 来 |
理学・工学の両方を学ぶので多種多様な業種への応用が利く。電気・電子機器、通信・コンピュータ関連、化学、鉄鋼、自動車といった製造業で活躍する一方、データ分析能力を生かして金融・保険業界に進む人もいる。 |

40.応用化学
化学の知識で、新しい素材や物質をつくる
応用化学は、これまでに得られた化学の知識を活用し、生活や文化を豊かにするための素材や材料、物質を開発する学問である。化学が、物質そのものの性質や構造を分析し、反応、合成などの実験や理論研究が中心なのに対して、応用化学は実際の製品やそれに用いられる技術を研究・開発することをめざす。
新素材の開発から環境保全にも取り組む
化学理論に工学的な要素をまじえて、物質の実用化に向けて実践的な研究を行う。電子材料、セラミックス、生体材料、高分子材料、分子設計などの分野がある。また人工物質のなかには有害物質が存在することから、物質が生体や環境に及ぼす影響と環境保全技術の研究にも取り組んでいる。このように、応用化学の成果は医療、エレクトロニクス、食品、環境などの多岐にわたる分野に貢献している。
| 将 来 |
石油、合成繊維、樹脂、電気部品などの製造業、環境保護、エネルギー関連の企業で、研究者・技術者として製品開発や生産技術開発に関わったり、化学知識を基に製品販売で手腕を発揮するなど、フィールドは幅広い。 |

41.生物工学
産業や医学・薬学へ生物学の知識の応用をめざす
生物工学は「バイオテクノロジー」とも呼ばれる。細胞や遺伝子、生体の仕組みなどについて学び、生物学分野の基礎研究で解明された生命のメカニズムを利用して、新しい物質や技術を開発し、産業や医学・薬学への応用をめざす工学的な学問である。主な分野は「遺伝子工学」と「細胞工学」の2つ。
遺伝子や細胞の謎を解明し、新技術を開発する
「遺伝子工学」は遺伝子の組み換え技術によって生物に新たな特徴や性質を与え、遺伝子の解析などを行うもので、作物の品種改良や人間の遺伝子治療などにも関わる。「細胞工学」は、マイクロインジェクション(細胞への遺伝子注入)の技術で特定の細胞の状態を作り出したり、がんの原因の解明をめざす研究なども行われている。生命や自然への影響に関わる研究も多く、その倫理観が問われる学問分野である。
| 将 来 |
医薬品・食品・化粧品・醸造などの企業や、厚生労働省・経済産業省・環境省などの省庁、国立の研究所にも進んでいる。なお、企業での研究職には修士の学位が求められることが多く、高い専門性が必要とされる。 |

42.資源・エネルギー工学
資源の開発と有効利用を考える「資源工学」
資源工学は、石油・天然ガス・メタンハイドレートといった地球の岩石層にある地下資源を研究対象とする。地盤の地質、鉱床を分析することで資源を探査・調査し、鉱物資源の開発・採掘、分離・精製などについて研究をする。それに加え、資源の利用にともなう環境問題や資源のリサイクルなどを考慮して、地球と人類の未来を視野に入れた研究も行う。
将来のエネルギーを探究する「エネルギー工学」
エネルギー工学では、化石燃料の有効で安全な利用のための方法やそのための機器の開発、利用によって発生する環境汚染物質に対する対策の研究分野、原子力発電の技術と安全性に関する分野、太陽光・風力・地熱・バイオマスといったクリーンエネルギーの有効利用によって地球環境を守るために、再生可能エネルギーに関する新技術を開発する分野などがある。
| 将 来 |
資源工学では、地質学・資源工学の知識を生かせる石油、ガス、地質コンサルタント会社や材料工学の知識を生かせる金属工業、鉱業などの分野に進む人が多い。エネルギー工学では、電力会社、原子力関連産業、重工業や電機メーカーへ就職する人が多い。 |

43.経営工学
工学的な手法で経営の問題を解決する
経営工学は、企業経営の効率化を図るために、人材・モノ・金・情報という経営資源をどう使えばいいかを、工学的な手法を使って研究する学問。企業の組織・生産設備・製造工程・品質管理・流通・販売などのあらゆる側面から研究を進めていく。現代の企業経営においては経営に関する専門知識だけではなく、コンピュータを活用した情報分析や生産・販売のシステムの構築などの知識が必要で、その両方を備えた人材が求められている。
さまざまな角度から経営をサポートする
研究テーマは、生産や流通における「技術革新」、効率のよく質の高い製品を製造するための「生産・品質管理」、経営上の的確な意思決定をするための「情報の活用」に関する研究、企業の経営状態の分析・評価を行う「経営管理」、事故の予防や職場環境の改善のための「人間工学」の研究などがある。
| 将 来 |
各種製造業、コンサルタント、シンクタンク、銀行、商社、販売・流通など、就職先は幅広い。コンピュータ技術のノウハウにより、システムエンジニアとして迎えられる人もいる。起業家や独立開業をめざす人もいる。 |

44.船舶・海洋工学
船と海に関わるさまざまな知識を学ぶ
船舶・海洋工学は、地球規模で海と人間に関わる幅広いテーマを対象とする。船舶系・海上海洋系・環境系の3つの分野に分かれている。
「船舶系」「海上海洋系」「環境系」で学ぶ内容
「船舶系」は、船舶を中心とした構造物の設計や建造、船舶の運航に関する研究を行う。船舶の構造に関しては、物理的な基礎理論を機械・電気・流体力学・制御などの工学分野から学ぶ。「海上海洋系」は、海洋資源の探索・開発、海底油田の石油掘削プラントや海上空港、海上リゾートなどのレジャー関連施設などの建設に加え、海上輸送システム、船舶による国際物流などについても学ぶ。「環境系」は、海の潮流や波など自然現象を解明し、海洋環境の保全や水域の有効利用につなげるための研究を行う。国土を海に囲まれた日本にとって船舶と海洋の利用は重要なものとなっている。
| 将 来 |
造船・輸送機械、重機械工業、海運業で船舶の製造や海上輸送に関する分野のほか、自動車、建設、航空、運輸、倉庫、通信などバラエティに富んだ業界に進んでいる。海技士免許を取得し、世界の海で活躍する人もいる。 |

46.農学・農芸化学
作物の生産から環境分野まで幅広く学ぶ「農学」
農学は、作物の品質の向上や生産量の増加などに寄与してきた長い歴史を有する学問。伝統的な品種改良だけではなく、遺伝子組み換えなどのバイオテクノロジーの導入による農産物の生産量の拡大や品質向上の探究も行われている。研究分野としては、遺伝、育種、園芸作物、果樹栽培、土壌などの基礎研究のほかに、環境保全や都市計画分野、農業関連のビジネスや農産物の流通システムの開発までと対象は幅広い。
化学の力を農学分野で生かす「農芸化学」
農芸化学は、農学系の学問の中の一分野で、農作物の機能や栄養成分の研究、栽培土壌や肥料・農薬の研究、食品の加工技術の開発などの研究分野がある。その成果は食糧(食品)、医療、環境などの分野にも応用されている。生物学や生命科学とも関係が深く、環境保全や食糧問題に貢献できる学問である。
| 将 来 |
農業、造園、園芸・種苗のほか、農業資材や食品関連産業へ。教職に就く人も多い。農芸化学系は、飲料・酒造、食品加工、医薬品分野が代表的。バイオ産業の発展で、金融やコンサルタント業界でも需要が高まっている。 |

47.農業工学・林学
効率的な農業のあり方を考える「農業工学」
農業工学は、効率よく農産物を生産するための技術開発や農地の整備、栽培設備の改善などに取り組む学問である。農業環境の悪化、農村の過疎化などの農村地域の生活環境の問題解決も目的としている。土地の有効利用や水資源の開発を主要テーマとする「農業土木分野」、農業生産に必要な機械や設備の開発に取り組む「農業機械分野」、資源の有効利用と生態系保全を考える「環境系」の3分野がある。
森林資源の保全や環境問題に取り組む「林学」
林学は、森林資源の活用と保全を地形・地質・土壌・気象などの自然科学と、経済・経営・社会学などの社会科学の両面から学ぶ。森林は木材を産出するだけでなく、二酸化炭素を吸収し、雨水を貯え、生態系を維持するという環境を守る機能を果たしているので、防災や環境問題の観点からの研究も行われている。
| 将 来 |
農業工学の土木系は官公庁などの公的機関や建築業、設計コンサルタントへの就職が多い。機械系は農機・建設機械・自動車などの製造業が中心。林学は林野庁や自治体の林務関連行政職の人気が高く、製紙会社やハウスメーカーなども対象となる。 |

48.農業経済学
農業を経済・経営・社会学的な視点からとらえる
農業経済学は、社会科学的な視点から日本や世界の食糧問題・農業の問題を研究する応用経済学という側面がある。例えば、農業政策論では、日本や世界の農業政策の歴史を振り返ったり、現在の農業が置かれている状況、高齢化が進む地域での農地の荒廃の問題などの解決策を探っていく。農業生産や所得の向上、農村地域の振興のためのブランド食材の開発や流通ルートの開拓なども研究対象となる。
農業が抱える問題の解決への道筋を探る
農業経営への株式会社の進出や、農協といった組織を研究することもできる。さらに、研究対象は日本の国内問題だけにとどまらず、重要な問題となっている農産物の貿易自由化や日本の食糧需給率の低下にともなう食糧の安全保障の問題など、国際的な視野もふまえて農業が抱えている課題に取り組んでいく。
| 将 来 |
農学と社会科学の両方の学問の習得により、全国農業組合連合会、農協などの農業関連団体、食品・流通・販売といった業種のアグリビジネスへ進む人が多い。環境関連、運輸やエネルギー関連の企業に進む人もいる。 |

49.獣医学
診断・治療・予防で動物の命を守る
獣医学は6年制のカリキュラムを基本として、産業用動物やペットの病気の診断や予防、治療を行う獣医師をめざす。BSE(牛海綿状脳症)、鳥インフルエンザなど家畜の伝染病の発生は深刻な問題で、その予防など病気への対応は、獣医師の重要な職務である。しかし、獣医師の活躍のフィールドは、動物の診察や治療だけにはとどまらない。
広汎なフィールドで活躍する獣医師
獣医師の職域としては、食品の衛生検査・監督・指導、動物用・人体用の医薬品の開発研究、野生動物の生態調査やその保護、バイオテクノロジー分野の研究など、一般的な獣医師のイメージではとらえきれない活躍の場がある。4年間のカリキュラムで動物病院の看護師や介助犬の養成などをめざす獣医保健看護学を学べる学科もある。
| 将 来 |
獣医などの専門職に就く人が大半。官公庁の公衆衛生や畜産部門、農業団体、競馬関連公的機関への就職も人気がある。民間企業では、畜産、乳業、飼料、食品メーカーでのスペシャリストとしての活躍が期待されている。 |

50.酪農・畜産学
家畜を育成し乳製品や食肉加工品を生産する
酪農・畜産学は、牛・豚・鶏といった家畜動物の生態や遺伝、繁殖などを研究し、肉や卵、牛乳や乳製品、加工食品の生産・製造技術を向上させ、安定的に供給・流通させることをめざす学問である。
繁殖から生育、製品流通や経営までを学ぶ
酪農学では乳牛や羊などの育成と牛乳の生産技術、その加工技術、経営や流通について学ぶ。畜産学では、遺伝子や分子レベルの研究などから家畜動物の生育や生殖について研究し、育種・繁殖・飼育の技術開発を行う。肉、卵などの生産・製品開発・流通や家畜のための飼料開発や畜産農家の経営に関しても学ぶ。また、野生動物の生態系保存や新種の実験動物の開発、アニマルセラピーなどによる動物の癒やし効果なども研究テーマとなってきている。
| 将 来 |
食品、畜産、飼料などのメーカーで、バイオ技術や遺伝子組み換え技術を応用するエキスパートとして期待されている。観光牧場、ペット産業や農業関連団体、アニマルセラピーの研究を生かして福祉分野に進む人もいる。 |

51.水産学
貴重な水産生物資源を守り育てる
水産学では、海や河川の有効利用および、魚介類などの水産生物資源の生産技術を学ぶ。特に海洋生物資源の状況は乱獲や環境の変化によって厳しい状況に追い込まれ、国際的に捕獲が禁止されたり、漁獲量制限の動きもある。そのため、「獲る漁業」から「育て、増やす漁業」への転換を図り、魚の品種改良や海洋環境保全の研究も進んでいる。
資源の有効活用に関する幅広い研究
研究分野は、漁業・水産資源学、水産環境学、増養殖学、食品生産学などに分かれている。廃棄されたり、これまで利用されてこなかった海洋性プランクトンや魚、海藻などの水産資源の有効活用を研究する分野では、有効成分の抽出などの研究が成果を上げ、食品に限らず、化粧品や医薬品、エネルギー関連分野での資源利用も進んでいる。
| 将 来 |
水産会社、食品産業、流通業、水産科学関連企業などで研究者や技術者として活躍。そのほか、養殖場、海洋環境調査会社、水質検査会社、漁業組合などが挙げられる。難関ではあるが、水族館への就職希望者も少なくない。 |
cFROMPAGE