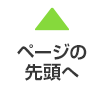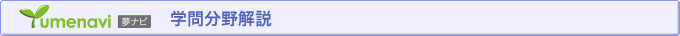学問分野解説

14.法学
法律の解釈や運用を学ぶ
法学は生活全般に関わる法律の成り立ちや解釈を学び、社会の問題に対する合理的な解決策を探る学問である。六法(憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)、行政法、労働法、国際法などの条文の解釈や、その法律がどのように運用されているのかを学ぶ。また、法律が社会正義にかなっているか、法と道徳はどう違うのかという哲学的な問題も扱う。
法的なものの見方や国際的な視点を養う
グローバル化により国際法や国際関係法の重要性が増している。また、企業経営ではコンプライアンス(法律遵守)が強く求められるなど、経済分野でも法律知識の必要性が高まっている。社会の複雑に絡み合う利害対立を調整する上で、法律の知識は欠かせないので、こうした問題に対処する「リーガルマインド(法的なものの見方)」を身につけた人材が、さまざまな分野で求められている。
| 将 来 |
法曹職や公務員などのほか、金融、商社、メーカー、マスコミなど、多岐にわたる。企業コンプライアンスの必要性から法律知識を有する人材へのニーズが高まり、企業の法実務のエキスパートとしての活躍も期待される。 |

15.政治学
国民を幸せにする政策を模索する学問
政治とは、公共的な問題の利害調整や意思決定の過程のことで、社会の秩序や枠組み、制度をつくり、問題を解決しながら維持していくためのものである。政治学が扱う領域は、政治の動向、地方自治、公共政策、選挙や住民投票、国際関係などと幅広い。国家や権力、政治行動や政治過程など政治を行う概念や作用を研究することが基本となる。
ダイナミックに世界と時代を動かす政治を学ぶ
政治制度などの歴史を学ぶ「政治史」、政治思想の流れを研究する「政治思想史」、さらに、外交や国際関係を扱う「国際政治学」や、ある国や地域の政治制度を研究・比較する「地域研究・比較政治学」という分野もある。また、「行政学」の分野では、国や地方自治体のあり方やその政策の立案、実施などについて研究していく。法律や社会学、経済学など関連する学問も合わせて幅広く学ぶことが多い。
| 将 来 |
進路は多岐にわたるが、政策面への理解が必要な報道機関や新聞社には、政治学を専攻していた人が比較的多い。公務員や、金融関係、流通・製造・サービス業などのさまざまな業界でも活躍している。 |

16.経済学
社会活動の根幹となる「経済現象」を研究する
経済学は、国家や世界の経済・景気がどのように変動していくかを、生産・流通・消費などの経済活動を分析したり、基本的な法則性を見いだしたりして経済の発展をめざす学問である。ただし、経済規模の拡大や生産量の増大だけを目的とするのではなく、富の分配のあり方を考えたり、より多くの人が豊かさを実感できる社会の実現をめざすための学問でもある。
経済のさまざまな現象を理論で考え検証する
マクロ経済学やミクロ経済学では、その理論をもとに、過去・現在の経済活動をさまざまな切り口で、実証分析しながら、将来の状況を予測する。ほかにも、経済活動に理論を当てはめてその正しさを検証する統計学・計量経済学や、現実社会でどのように経済理論を生かすかを検討する経済政策などの研究分野がある。グローバル化の進展の中で、経済学を学ぶ上では国際的な視野も重要になってきている。
| 将 来 |
進路の選択肢は幅広いが、学んだ知識を生かしやすい銀行・証券・保険などの金融関係、商社、メーカーへの就職が人気を集めている。資格取得で多いのが証券アナリストや税理士、中小企業診断士などである。 |

17.経営学・商学
企業活動の理論と実務を学ぶ「経営学」
経営学は企業の運営・管理で発生する「人・モノ・金」などに関する事象を分析することを目的としている。財務・生産・労務などの現状を把握した上で、目的達成のための手段や技法を学ぶ学問である。経済学との明確な区分は難しいが、経営学のほうが企業活動そのものを対象として、より実務的で具体的な分析や研究をする。
モノの生産から消費までの商業活動を学ぶ「商学」
商学は、商品の生産・流通・販売・消費の商業活動全般を研究対象とする。さらにマーケティングや貿易、金融〈銀行・証券・保険)について学ぶことができる。商学の一分野である会計学は、企業活動に必要な会計・簿記を研究するもので、財務会計・管理会計・税務会計などについて学ぶ。経営学・商学の両方とも、基礎的な経済学や民法・商法、会計学などを学ぶのが一般的である。
| 将 来 |
事務系職種のほとんどは学んだ内容と関連しているため、進路は幅広い。一般企業では、流通、商社、メーカー、金融の分野に進む人が多い。国家試験を受けて公認会計士や税理士などをめざす人も少なくない。 |

18.経営情報学
企業経営に必要な「情報」の扱い方を学ぶ
経営情報学は、社会にあふれる情報の中から企業経営に必要な情報を選択して収集し、経営の分析や意思決定に役立てることを目的とする学問。経営学が研究対象としている「人・モノ・金」に加えて「情報」という要素を研究の中心に据えていることがこの学問の大きな特徴である。ネットワークシステムの発達で情報の重要性はますます高まっている。
理系的なセンスや能力を「経営」に生かす
組織の管理や運営といった文系的側面に加え、コンピュータによる情報処理やデータ分析という理系的側面の両面から学ぶことになる。経営の意味や組織のあり方を考える経営学理論をふまえて、データの収集・分析によって経営システムの開発や構築をめざしたり、経営マネジメントや企業の経営戦略立案の方法なども研究対象となる。プログラミングやシステム設計など情報処理の能力が大いに発揮できる分野だ。
| 将 来 |
経営学的な知識に加え、情報・コンピュータ科学の分野にも通じた人材として、企業での期待度が高まっている。情報処理系企業をはじめ、金融・サービス関連企業・広告代理店などへの就職が目立つ。 |

19.社会学
社会や人間の営みを深く探究する
社会学は「集団の一員としての人間」という観点から、個人を取り巻くあらゆる社会関係や、その中での人間の営みを探究し、人間の行為とその意味を客観的に分析する。家族や学校、企業、地域社会の問題から、都市、産業、メディア、文化、国際社会、人類のテーマまで多彩であり、「人間の集団と関わりのある事象」はすべて社会学の研究対象となる。
幅広い研究対象とフィールドワークなどが特徴
また具体的な研究対象は幅広く、「格差問題」「非正規雇用」「命の尊厳」「ジェンダー」「テロリズム」「SNS」「過疎化」「まちづくり」など、社会に起こっている現象や問題を取り上げて分析し、提言や注意喚起を行っていく。社会学では、研究する目的の場所に出かけて、情報収集のためのアンケートやインタビューなどの聞き取り調査を行う「フィールドワーク」を重視するという特徴がある。
| 将 来 |
学んだことを実践できる就職先はバラエティに富んでいる。メーカーや小売業で商品開発や販売戦略を手がけたり、情報収集が欠かせないマスコミやマーケティング関係、公務員として公共の問題の解決に携わる人もいる。 |

20.社会福祉学
人々の暮らしと社会の未来を支える
超高齢化・少子化・格差の拡大が進む日本において、重要性の高まる福祉について理論と実践をトータルに学ぶのが社会福祉学。荒廃した地域社会の再建や都市社会の環境整備、医療福祉制度や法律の整備、具体的なソーシャルサービスから社会全体を視野に入れた理論まで、政治、法律、社会、医療などの側面から幅広く研究する。
すべての人が「人間らしく」生きることをめざす
具体的には、老人福祉、障がい者福祉、児童福祉といった視点から、すべての人が人間らしく生きるための方法や社会制度のあり方について学んでいく。社会福祉の理論を学ぶだけではなく、社会福祉士や精神保健福祉士などのソーシャルワーカーや、介護福祉士、ケアマネジャーなどの資格をとって、社会的な弱者を支えていく人材を育成している。
| 将 来 |
ソーシャルワーカー、公的機関の職員など福祉の現場を志望する人が多い。社会福祉士や介護福祉士の受験資格を取得し、国家試験に合格すれば、福祉事務所や児童相談所、老人介護施設などの社会福祉施設で活躍できる。 |

21.環境学
人間や生物が豊かな営みを続けていくための学問
水や大気、土壌や気温、自然や景観など人間と環境の関係を掘り下げて研究するのが環境学である。環境については、これまで生物学や、農学、地球科学などの自然科学系の学問で研究されてきたが、環境問題は経済や法律、社会制度などとも絡み合っているため、人文・社会学系のアプローチによる研究も求められるようになってきている。
文系・理系の両面からのアプローチで環境を守る
人文・社会学系では、環境と人間生活との関わりを考えるための法整備や政策の立案、経済的な側面からの問題解決の探究や仕組みづくりなどがテーマになる。理系的アプローチでは、既存の自然科学的分野に加えて環境計画学や環境デザイン学なども学ぶ。ゴミ処理やリサイクルなどの身近な問題から、酸性雨や温暖化、PM2.5といった地球レベルの問題まで、さまざまなテーマが対象になる。
| 将 来 |
理系・文系にまたがる学問なので、就職先も多岐にわたる。製造、建築、エネルギー、サービス、飲食などの一般企業、マスコミ関係、自治体、公益法人、環境NGOなどでの活躍が期待される。公務員になり、行政機関・教育機関で働く人もいる。 |

22.観光学
「おもてなし」の心で観光文化を生み出す
観光学では、「現代における観光の役割」「観光地での地域文化との触れ合い」「ホスピタリティの重要性」など、観光と関わりをもつ社会現象に関連する研究を行う。観光を地理学、経済学、社会学、人類学などさまざまな学際的見地からとらえ、豊かな観光文化を築くための探究をすることにより、観光産業に関連する諸問題の解決にあたる。
観光を文化と産業の両面から学ぶ
具体的には、「観光文化や観光行動に関する分析や研究をする分野」「観光地の開発や観光地の運営を地域発展に生かす研究をする分野」「ホテルやレジャー施設、テーマパークといった観光関連施設や企業の研究をする分野」などがある。文化としての観光という側面だけではなく、産業としての観光についても研究対象とする。また、理論だけではなく、観光業に必要となる語学や実務や技能についても学ぶ。
| 将 来 |
ツアーコンダクター、ツアープランナーなどの観光・旅行業界やホテルスタッフ、コンシェルジュといったホテル業界、テーマパーク、アウトドア、レジャー・スポーツ関連など、サービス業界全般で活躍する人が多い。 |

23.マスコミ学
時代の動きを見つめ、情報を発信する
マスコミュニケーション全般とテレビ・ラジオ、新聞・雑誌、出版、広告、インターネットといった各マスメディアについて、社会における役割や影響力、情報伝達の仕組みや歴史などを学ぶとともに、制作や情報発信に関する技術まで視野に入れて専門的に研究する。また、企業などの広報活動について、その役割やメディアとの関係なども研究する。
情報メディアの役割やそのあり方を探究する
具体的には、2つの方向性がある。ひとつはマスメディアの役割やそのあり方そのものを追究するアプローチ。マスメディアが伝える情報の内容の検証や、社会に与える影響の分析によって、情報発信のあるべき姿を探る。もうひとつは、新聞、出版、広告、インターネットなど特定のメディアについて、その役割や問題点などを研究するアプローチだ。知識や理論だけではなくメディアの倫理的な側面も研究対象となる。
| 将 来 |
学んだ内容を直接生かせる新聞社、放送局、出版社などのマスコミ関連企業や広告業界への就職をめざす人に加え、一般企業の広報部門や広告宣伝部門、制作部門で活躍する人も多い。 |

24.国際関係学
グローバル化する世界を広い視野で考える
グローバル化が進む中で、1つの国だけでは解決できない問題が起こっている。複雑に絡み合うこうした国際的諸問題を多角的な視点から研究するのが国際関係学。戦争や民族紛争、貿易問題などを通して国家間の政治経済関係や国際平和を追究する社会科学的アプローチと、異なる民族や地域の問題を国家・国境を超えて考える人文科学的アプローチがある。
国際舞台で活躍するための知識を身につける
研究には、政治学、法学、経済学、史学、地理学、社会学などの分野の知識が必要であり、語学力も要求される。その研究対象は、主権国家だけには限定されず、EUやASEANなどの国際共同体、国連などの国際機関、NGO、多国籍企業など広範囲に及ぶ。平和の構築や温暖化などの環境問題、多国間での貿易の枠組み作りや企業の海外進出の問題、多文化共生のあり方などテーマは多岐にわたる。
| 将 来 |
語学力や国際感覚を生かし、外資系の企業、金融関係、製造業、商社、旅行会社、マスコミなど、就職先は多岐にわたる。NGOやシンクタンクでの国際貢献を希望する人、海外留学や大学院進学をする人も増えている。 |

25.情報学
高度に情報化する社会の問題を解決する
インターネットやスマホの普及で情報関連分野では、さまざまな新しい技術やサービスが生まれ、トラブルも増えている。それにともない、従来は理工系学部で研究されてきた分野だが、文科系の視点からのアプローチの必要性も高まり、情報学を学べる文科系の学部も増えている。コンピュータ理論や仕組み、プログラミングを学ぶ分野、情報の収集・分析・処理技術などを学ぶ分野、情報と社会の関係を学ぶ分野などに大別される。
文系、理系それぞれのアプローチで情報を生かす
文科系学部では、情報技術の理論や知識と情報収集・情報解析などの実践的技術を習得し、情報を活用した問題解決手法を学ぶ。理学系学部では認知科学や情報統計学、情報処理論など原理的研究が中心。工学系学部ではコンピュータに関する研究をベースに、AI(人工知能)やネットワークの構築などを学ぶ。
| 将 来 |
企業の情報関連部門、IT関連・メディア系・金融関係を含む広範な業界・業種への就職が可能。理工系はソフトウェア開発・情報通信・情報サービス分野の企業や電機・コンピュータメーカーなどに就職する人が多い。 |

26.メディア学
進歩するメディアと多彩な表現について学ぶ
映像・音声・文字・写真などを表現するメディア全般について、それぞれの機能や特徴、役割を学ぶとともに、デジタル表現を中心とするさまざまな表現技術や情報伝達技術をクリエイティブな要素も含めて総合的に研究する。テレビのデジタル放送による双方向性メディアの誕生や電子書籍などの登場でメディアが提供する情報の形も変化しつつある。
メディアの問題点や未来を考える
インターネットやスマホなどの通信手段の発達によって、テレビやラジオ、新聞などのマスメディアだけではなく、個人と個人がつながるLINEやツイッターなどのSNSやオンラインゲームなどメディアは多様化している。個人が情報発信する動画コンテンツやネット上での発言もメディアとしての役割を持つようになってきている。このような変容するメディアについての問題点やメディアが社会をどう変えていくかなどについて学ぶ。
| 将 来 |
CGデザイナーやゲームクリエイター、Webデザイナー、サウンドクリエイターなど専門職や、マスコミ・出版関係、インターネット関連企業への就職をめざす人が多い。企業の広告宣伝部門や制作部門で活躍する人もいる。 |
cFROMPAGE