|
 |
| 数や図形等の性質・関係を研究して、公式・証明等の法則化を図る論理的思考の学問。抽象的な概念を論理的に考える理論体系を主とし、代数学・幾何学・解析学等を究める「純粋数学」、コンピュータを積極的に活用して社会科学の諸問題を数値化する等、自然科学、社会科学や工業分野と関連して発展する「応用数学」がある。 |
|
主な就職先にはシステムエンジニアやプログラマーをはじめ、製造業や情報通信等のサービス業、金融関係、公務員等が挙げられる。教員免許の取得が可能なことから、教職への就職も多い。また他学系に比べて大学院への進学率が高く、修士課程修了後に一般企業へ就職する場合が多い。 |
|
| |
数学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 自然界で生じている物理現象の観測と実験的検証を通して、各々の現象がもつ法則を証明し、理論的解釈を与えることを目的とする学問。対象は非常に幅広く、宇宙、地球から、ミクロの世界の分子、原子、素粒子まで自然界のすべての事象を範疇とし、半導体や超電導等をはじめとする科学技術への応用範囲は広い。 |
|
大学院への進学率が半数に近く、修士課程の後に企業の研究部門への就職を見据える例が一般的。さらにエキスパートをめざし、大学や国の研究機関に就職する人もいる。一般企業の職種としては、電子機器、機械等のメーカーをはじめ、ソフトウェア、システムや情報分野が中心だ。 |
|
| |
物理学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 身の回りに存在するあらゆる物質とその性質や化学変化の仕組みを調べて分析し、人間の暮らしに役立つ新しい物質を作り出していく。バイオや光通信といった多彩な分野に接点をもつ。薬品や新素材、半導体、セラミック等の開発につながる物質研究をはじめ、物質と環境の関わりを分析して環境保全技術を開発する等、広範囲に応用できる。 |
|
一般化学産業以外にも、金属・医薬品・食品を扱う企業等、就職の選択肢は広い。専門書を扱う出版業界や金融業界などへ進む人も少なくない。企業研究者のような専門家としての就職をめざすならば、大学院を修了してより高度な知識を身につけることが望ましい。 |
|
| |
化学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 人間・動物・植物・微生物・ウイルス等すべての生命体を対象に、自然界での活動や、個々の生体現象の解明を探究する。遺伝子のレベルから細胞、生物の内部器官まで、ミクロからマクロな視点にわたり、進化の道筋をたどったり、生命の誕生の仕組み、生態と環境との関係を追究する等、アプローチ方法はさまざまだ。 |
|
企業に就職するにしても、高い専門性が必要となるため、大学院の修士課程に進む人が大半を占める。研究者として大学に残るほか、環境省や遺伝学研究所といった公的機関に入る場合もある。一般就職の業種としては、医薬品・食品・化粧品・醸造等の分野で商品開発という進路が開けている。 |
|
| |
生物学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
|
温暖化やオゾンホール、エネルギー問題等、地球の未来を左右する自然現象の問題解決をめざすための学問。そのベースとなる分野研究のスケールは大きく、地球の誕生から現在までが対象。地層や化石、気象、生物を手がかりに、地球そのものの存在について解き明かしていく。応用分野は防災や環境保全、天然資源開発等。 |
|
将来のフィールド
多くの人が大学院へ進学した後に、環境計画・都市計画関連企業、エネルギー関連企業、土木・建設関連企業等で専門職に就いている。最近は、データ解析能力を活かしてIT産業や製薬会社への就職も目立つ。公務員では、建設・土木・気象等を扱う省庁へ進出している。 |
|
| |
地球科学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 機械技術の原理や方法論を系統立てて研究し、機械やシステムを構築するためのテクノロジーを学ぶ。材料系、熱・流体系、設計・製作系、計測・制御系の4分野に分かれ、対象は工作機械、発電、精密医療機器・マイクロマシン等、スケール・種類ともに幅広い。人工知能・臓器の開発等、異分野の研究との関わりも深い。 |
|
業種としては、自動車や造船、家電といった機械関連、重工業等が挙げられる。また機械工学の知識が生産技術の各方面で求められることから、食品・繊維等多様な製造業で活躍できる。研究職での就職を希望する場合は大学院進学を検討したい。 |
|
| |
機械工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 「大空への夢」を実現した航空・宇宙工学は、航空機やロケット開発、宇宙ステーション計画等に必要な先端科学技術を生み出す、スケールの大きな学問。流体力学、構造力学、推進工学、航行・制御工学の4分野とシステムとの組み合わせから成り立つ。進歩が著しいだけに、常に新たな課題に取り組める創造的なカリキュラムが用意されている。 |
|
航空機メーカーや航空会社のほか、工業用・動力用などの電機メーカーの宇宙・ロボット部門、精密機器メーカー、鉄道関連企業等フィールドは広く、航空機の整備やパイロットの資格取得を見据えた就職も多い。宇宙航空研究開発機構や航空宇宙関連の研究所、関連官公庁等の公的機関にも進出している。 |
|
| |
航空・宇宙工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| エネルギーと情報伝達媒体という、電気がもつ2つの側面を研究の軸とする。電気工学は電子の流れをエネルギーとしてとらえ、主に発電、電力輸送、電動機の制御等について学ぶ。電子工学は情報伝達の媒体としての電子を考えるもので、コンピュータや電子機器製作の基礎となる学問。ソフト・ハードやネットワーク技術の開発といった、電子の性質の応用に関わる。 |
|
家電製品やコンピュータのハードウェア等のエレクトロニクス、情報関連産業、エネルギー関係はもとより、通信、ソフトウェア、材料関連の産業、金融機関等で技術開発に携わっている。大学院への進学率も高い。 |
|
| |
電気・電子工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
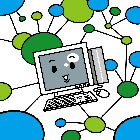 |
|
コンピュータ、情報、通信に関するあらゆる技術を研究する。主要テーマの1つ目はコンピュータのハード・ソフトと通信・情報処理の総合的な観点からの研究。2つ目は情報そのものを多面的に取り上げ、確率・統計等の情報理論、ソフトについて学ぶ。3つ目は産業部門への応用を図る分野で、管理工学・経営理学・経営工学等がこれにあたる。 |
|
システムエンジニアといった直接情報に関わる職業は言うまでもなく、オーディオや家電等の電気・電子機器メーカー、金融や流通、製造、サービス等各方面の企業がターゲット。ただし、即戦力をめざすなら修士課程への進学を視野に入れた方がよい。 |
|
| |
通信・情報工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 芸術と融合した科学として、機能性・快適性・強さや安全性、環境に合った美しさを基本とする建物を作る知識・技術を習得する。大きく分けて設計の基本となる計画系、耐震等の具体的な技術や材料について学ぶ構造系、光、音、空気等の役割を研究する環境系の3つの分野があり、設計にはこれらの総合力、空間表現、デザイン力が要求される。 |
|
ゼネコンや設計事務所での設計および構造計算、現場での施工・管理に携わったり、官公庁に所属して都市計画に関わる等の職種がある。実務に関わりながら建築士をめざす人も多い。建築関係以外では、広告や金融、不動産関連等にも就職している。 |
|
| |
建築学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 道路・鉄道・橋等の交通施設、発電所等のエネルギー施設、河川海岸堤防・上下水道・ダム等のライフラインを構築する技術を研究する。そこに欠かせないのが、自然環境と人間生活との調和を図った社会システム形成というソフトウェア系の視点だ。住みよい社会環境をつくるため、都市や地域のレベルにとどまらず、地球工学的な研究も多い。 |
|
土木工学系卒業者の大半は、ゼネコンで公共工事プロジェクトに従事する。鉄道・不動産・コンサルタント等の業種でも知識と技術を活かせる。環境工学系の場合は、土木工学系と同じ分野への進出のほかに、上下水道整備の企画・設計を請け負うコンサルタント会社に勤める割合も高い。 |
|
| |
土木・環境工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 新素材を中心にモノを構成する材料について、その構造・機能を工学的に解明し、それに基づく新機能の発見、材料を製造するプロセスから実用化するための開発技術までを広範に学ぶ。近年は材料と環境との調和という観点をふまえ、製造・加工から利用、リサイクル・廃棄に至る高機能材料の開発と、ライフサイクルについての研究に重点が置かれている。 |
|
製鉄・非鉄金属会社、商社の鉄鋼貿易部門等が、従来から即戦力として期待される分野だ。最近は多種多様な産業分野で技術の複合化が著しいことから、電気・機械・自動車・繊維・石油・化学等の業種に就く例も少なくない。 |
|
| |
材料工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 半導体研究からトランジスタが生まれ、IT産業に発展したように、物理理論を基に新技術の開発を進める学問。代表的な分野は、電子素子物理・電気回路について研究するエレクトロニクス、情報理論に基づく情報制御等がある。機械、材料、情報等の領域から学ぶが、純粋物理学とは異なり工学的な科目が中心となっている。 |
|
理学・工学双方にまたがる知識を身につけることから、多種多様な業種への応用が利く。電気・電子機器、通信・コンピュータ関連、化学、鉄鋼、自動車をはじめとした製造業で活躍する一方、データ分析能力を活かして金融・保険業界等で実績を積む人も多い。 |
|
| |
応用物理学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 化学理論に工学的な要素をまじえて、物質利用の実用化をめざす実践的な研究を行う。生体材料、電子材料、セラミックス、分子設計等のテーマから、物質の構造と化学反応を利用した新素材の開発を目的としている。また人工物質のなかに有害物質が存在することから、物質が生体・環境へ及ぼす影響と環境保全技術の研究も併せて取り組んでいる。 |
|
石油、合成繊維、樹脂、電気部品等の製造業をはじめ、環境保護、エネルギー関連の企業に迎えられている。研究者・技術者として製品開発や生産技術開発に関わったり、化学知識を基に製品販売で手腕を発揮する等、フィールドは幅広い。 |
|
| |
応用化学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 2本の柱があり、その1つは多種多様な生命現象や生体の機能等を解明する生物学的な分野。もう1つは解明された生命のメカニズムを利用して、新しい物質や技術を開発し、産業や医学・薬学への応用をめざす工学的な分野だ。理学・工学・農学・医学等の領域を有機的に統合しながら、学問体系と物質・技術の双方のモノづくりをめざす学問である。 |
|
専門分野に直接関わる進路は、医薬品・食品・化粧品・醸造等の企業。厚生労働省・経済産業省・環境省等の省庁、国立の研究所等にも進んでいる。なお、企業での研究職には修士の学位が求められる等、高い専門性が必要とされる。 |
|
| |
生物工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 地球環境との共存と次世代エネルギーの開発をめざす学問。資源工学では、資源の探査・開発・処理という既存の分野に加えて、資源の利用に伴う環境問題、自然災害の予測等、地球と人類の未来を視野に入れた研究を行う。エネルギー工学では、エネルギー利用の基礎および、原子力、太陽光等、高品位エネルギーを応用する新技術開発に重点を置いている。 |
|
資源工学系の進路としては、石油、ガス、地質コンサルタント会社で地質学、資源工学を、金属工業、鉱業等の分野で材料工学の知識を活かすことができる。エネルギー工学系は、電力会社、原子力関連産業、重工業や電機メーカーへの就職が中心だ。 |
|
| |
資源・エネルギー工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 経営の効率化を図るために、モノ・人材・情報といった経営資源を使って、新製品やサービスを生み出す手法を研究する。最近の企業経営にはIT技術が不可欠なことから、コンピュータによる情報処理を中心とした生産・販売管理システムの構築もこの分野の大きなテーマ。品質管理、財務管理、経営分析、環境工学等も研究する。 |
|
各種製造業をはじめ、コンサルタント、シンクタンク、銀行、商社、販売・流通等、知識と技術を発揮できる分野は多種多様だ。コンピュータ技術のノウハウにより、システムエンジニアとして迎えられる卒業生も多く、ベンチャービジネス企業家や独立開業をめざすケースも珍しくない。 |
|
| |
経営工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 船舶を中心とした構造物のシステムおよび、海洋環境をはじめとする自然のシステムをテーマに、土木・建築等多角的な視点からアプローチする学問。船舶の構造に関する物理的な基礎理論を学ぶ船舶系、海上都市等の海洋開発に必要な専門知識を身につける海上海洋系、海水の基本性質を海洋環境・水域利用や油田開発等に応用する環境系の3つの主な領域がある。 |
|
造船・輸送機械、重機械工業、海運業で船舶の製造や海上輸送に関する分野のほか、自動車、建設、航空、運輸、倉庫、通信等バラエティに富んだ業界で習得した知識を応用することができる。船舶職員の免許を取得し、世界の海で活躍する人もいる。 |
|
| |
船舶・海洋工学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
|
|
 |
| 動植物を中心とした食糧資源の生産・加工および流通の効率化を促進してきたバイオテクノロジーを学ぶ。遺伝や染色体解析等、生物学的な要素も含む。研究対象が資源や生命科学、環境学と多様化しており、さまざまな最先端技術を利用した生産技術開発、農業関連産業の経済・経営、環境保全、都市計画等広範囲をカバーしている。 |
|
農業、造園、園芸・種苗等の第一線で業績を上げているほか、農業資材や食品等の関連産業への進出が目立ち、教職に就く卒業生も多い。農芸化学系の一般就職では、飲料・酒造、食品加工、医薬品等の企業が代表的だ。バイオ産業の発展に伴い、金融やコンサルタント業界でも需要が高まっている。 |
|
| |
農学・農芸化学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 農業工学は農環境の悪化、農村の過疎化等の問題解決を目的とする。土地の有効利用と水資源の開発を主要テーマとする農業土木、生産に必要な機械の開発に取り組む農業機械、資源の有効利用と生態系保全という観点から農業のあり方を考える環境系の3分野が研究領域。一方、林学系では、森林資源の活用と保全について、自然科学・社会科学の両面から学ぶ。 |
|
専攻に応じて進路も分かれている。土木系は官公庁や公的機関へ所属する人が比較的多く、建築業、設計コンサルタントへの就職も多い。機械系は農機・建設機械・自動車メーカー等製造業が中心。林学卒業生は林野庁や自治体の林務局等行政職での人気が高い。 |
|
| |
農業工学・林学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 社会科学的な視点から日本や世界の食糧・農業を研究する学問。経済学理論を食糧と農業の問題に応用する応用経済学、さまざまな技術を農業の現場に伝える科学としての農学という2つの側面がある。政策、歴史、経営、流通等の見地から農業を分析し、世界貿易といった国際的な視野もふまえて、現在、農業が抱えている問題を認識していく。 |
|
農学と社会科学の両方の要素を含んだ学問の習得により、全国農業組合連合会・全国および地域の農協といった農業関連団体、食品・流通・販売といった業種のアグリビジネスへ進む卒業生が一般的。環境関連、運輸やエネルギー関連の企業へ入るケースもある。 |
|
| |
農業経済学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 動物の病気の治療・予防、飼育・生産方法、食品・環境の衛生、動物・人体用薬品開発、バイオテクノロジー等、研究領域は多岐にわたる。対象となる生き物も家畜からペット、実験動物、微生物等幅広い。また、動物との触れ合いや死による人間の心理状態の変化等、一歩踏み込んだ研究も注目されている。 |
|
専門職に就く人が大半を占めており、第一に挙げられるのはやはり獣医。官公庁の公衆衛生部門や畜産部門等公務や、農業団体、競馬関連等の公的機関への就職も人気がある。民間企業では、畜産、乳業、飼料、食品等のメーカーからの求人が多く、スペシャリストとしての活躍が期待されている。 |
|
| |
獣医学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 食品としての家畜動物の研究を通して、効率のよい生産と人間の食生活への利用を目的とする学問を展開する。酪農学系では生産技術、経営や流通、環境情報、食品加工について学ぶ。畜産学系では動物の成長や生殖の機能分析に加え、野生動物の生態系保存や新種の実験動物の開発等も範疇としている。 |
|
食品、畜産、飼料製造、ペットフード等のメーカーで、バイオ技術や遺伝子組み換え技術を応用できるエキスパートとして期待されている。観光牧場、動物実験受託機関、ペット産業といった動物を扱う業種や、農業関連団体、アニマルセラピーの研究を活かして福祉分野に進む等、多彩な道がある。 |
|
| |
酪農・畜産学系の夢ナビ講義を見る |
|
|
|
 |
| 海や河川等「水圏」の有効利用および、食糧資源の生産技術を学ぶ。その根幹となるのは、漁業、水産環境、養殖、食品加工・保存方法等を扱う生産・製造の分野である。「獲る漁業」から「育て、増やす漁業」への転換を図り、魚の品種改良や海洋環境保全等の研究も進んでいる。 |
|
水産会社をはじめとして、食品産業、流通業、水産科学関連企業等で研究者や技術者として活躍。そのほかの専門的な進路としては、養殖場、海洋環境調査会社、水質検査会社、漁業組合等が挙げられる。難関ではあるが、水族館への就職希望者も多い。 |
|
| |
水産学系の夢ナビ講義を見る |
|
|