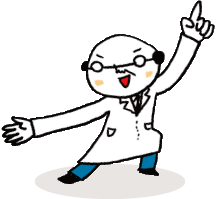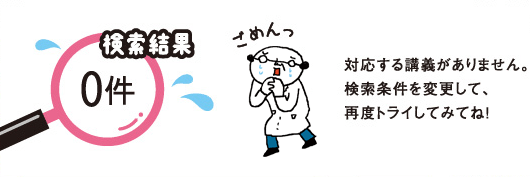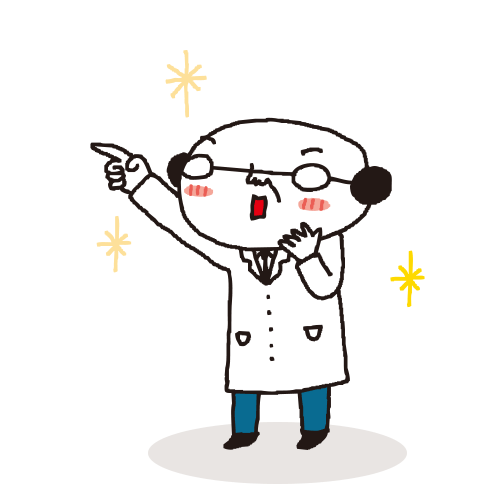
自分の興味・関心が
学問の世界へつながっている。
自分では気付いていない
学問への可能性がいっぱい!
まずはあなたが熱中できる
関心ワードから
探してみよう!


掲載講義数
6,877
本
提供教員数
6,103
名